外貨預金は今から始めていいの?預け入れと引き出しのタイミングを解説
本記事は、SBI新生銀行からのお知らせです。

外貨運用がこれからは必要な理由
2022年中には急激な円安が続き、瞬間的には1米ドル=150円に到達しました。同年9月、10月に政府・日銀が24年ぶりの円買いの為替介入を行ったことは記憶に新しいと思います。円だけでの資産運用はリスクかもしれないという不安もあり、将来の生活を守るための、資産運用の一環として外貨運用を考えている方が増えています。資産分散を目的として、という理由が一番大きいでしょう。 日本円の資産しか保有していない場合、円の価値が下がると、資産は相対的に減っていることを意味します。米ドルやその他の通貨に分散投資をすることは、円の価値下落に対する代表的な対応策となっています。
「円安、円高」ってよく聞くけど?
海外旅行へ行く時は、円をその行き先の国の通貨に交換します。例えば、ハワイ(米国)へ行くなら米ドルに、パリ(フランス)に行くならユーロに、という具合です。外貨の取引は日本円と外貨だけでなく、外貨と外貨でも行われます。例えばパリの人がハワイへ行く時は、ユーロを米ドルに交換します。
このように、さまざまな通貨を組み合わせた取引が世界中で常時行われています。そして、交換の比率(為替レート)は刻々と変わっていきます。例えば、ある時点の外国為替相場で米ドルと円の交換比率が「1米ドル=120円」だったら、1米ドルを買うのに120円必要ということです。
それが、その後「1米ドル=125円」になったら、1米ドル買うのに125円必要です。つまり、米ドルの価値が5円分上がった、言い換えれば円の価値が5円分下がったということになります。「円安(米ドル高)」になったわけです。逆に「1米ドル=115円」になったら、「1米ドル=120円」の時よりも少ない円で1米ドルが手に入るわけですから、米ドルの価値が下がり日本円の価値が上がったといえます。「円高(ドル安)」になったわけです。
「1米ドル=115円が120円になる」というように、円の数字が大きくなると「円安」で、「1米ドル=120円が115円になる」というように、円の数字が小さくなると「円高」ということになります。外貨投資をする上で、この点はしっかり覚えておく必要があります。
つまり「円の価値が上がれば円高、円の価値が下がれば円安」ですが、「円の数字が減ったら円高、円の数字が増えたら円安」と覚えると良いと思います。
円安は生活にも大きく影響する
そもそも「外国為替相場なんて、海外旅行に行く時しか関係ないよね」と思っている人も多いと思いますが、為替の変動は私たちの日常生活にも大きく影響しています。
日本は食糧や原油など、多くの物を海外から輸入していて、その代金の支払いには主に米ドルが使われます。同じ物を同じ量、輸入しても、円安になれば円の価値下がって支払う円の額は多くなってしまいます。
もし1万米ドルの商品代金を払うのに、「1米ドル=115円」なら115万円ですが、「1米ドル=120円」になると120万円が必要になるといった具合です。円安になると、海外から商品を輸入している会社は支払代金が多くなるため、それを商品価格に上乗せすることがあり、輸入品の国内販売価格が上がる傾向があります。
2022年から2023年にかけて、多くの食料品価格が上昇しました。円安による輸入物価の上昇は食料品価格上昇の要因の1つとなっていると思われます。
長期的な日本経済の状況にも注意
さらに日本はこれから人口の減少や高齢化が進むことによって労働人口が減り、経済力が弱くなったり、財政が悪化したりすることが懸念されています。そうなると、海外の投資家などが保有する円を売ることが考えられ、それが円安につながります。将来、円安が進むとしたら、輸入食品や原油などがさらに値上がりし私たちの生活に影響を及ぼします。また、持っている資産が「円」だけだと、相対的に資産が目減りすることになります。
こうしたことに備える方法の一つが、資産の一部を外貨で保有することです。円の価値が下がっても、外貨の価値が上がれば資産全体の目減りを抑えることができ、それを売却すれば為替差益が得られます。外貨投資は、お金を増やすためにも、資産を守るためにも必要といえるでしょう。とはいえ将来、円高になる可能性もあります。また、日本で生活していく以上は、円が中心です。したがって、外貨投資は資産の一定割合までにしていくことが大切です。
外貨預金を始めるタイミング(預け入れ)
外貨預金は、円預金よりも金利が高い傾向があるというメリットがある一方、元本割れのリスクなどのデメリットもあることも事実です。では、外貨預金を始める場合、そのタイミングはいつが良いのでしょうか。最適なタイミングは、さまざまな要素を踏まえて検討する必要があります。たとえば、現在の通貨レート、経済状況の他、個々の金融資産状況や投資の目的・目標額なども判断材料になります。
通貨レート
外貨預金を検討している国の通貨が、日本円に対して低いレートで取引されている場合、購入の良い時期かもしれません。
たとえば、過去30年を振り返ると下記チャートのとおり、米ドル円の為替レートが、1米ドル=100円を下回っている期間は、さほど多くありません。しかも、1米ドル=100円以下に円高が進んだ数年後には、米ドルは100円を超える水準に上昇していることがわかります。この為替チャートを見る限り、「100円以下で米ドルを買っておくのが投資においては正解だった」ということがわかります。

(出典)日本銀行 時系列統計データ 検索サイト 主要時系列統計データ集を基に筆者作成(https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/mtshtml/fm08_m_1.html)
しかし、仮に今後米ドル円為替レートが100円以下に落ちる(=円高米ドル安になる)ことがあったとしても、その後再び米ドル高になる保証はどこにもありません。
通貨の価値は、その国の経済状況、政治的安定性などによることを踏まえたうえで投資判断をすることが大切です。
政治経済状況
現在の国際経済状況や政治情勢など、予測される将来の動向を理解することは、外貨預金を開始するタイミングを決定する上でも重要となります。為替レートは、その国の政治情勢、経済成長、貿易関連、GDPなどの指標、インフレ率、金利などに大きく影響されます。
たとえば、先述の米ドル円為替レートのチャートを見ると、2021年から2023年にかけて急激に円安米ドル高が進んでいることがわかります。実は同時期に日本の貿易収支は赤字が進んでいました。貿易収支が赤字ということは、日本人が外貨を買って海外の物を買う取引の量が、外国人が円を買って日本の物を買う取引より多いということです。そのため、日本の貿易赤字は円安要因となるといわれています。近年の円安米ドル高の原因は貿易収支の赤字が1つの要因になっている可能性があります。
また、米国の中央銀行FRBは、2022年3月から本記事執筆時点の2023年5月現在にかけて、複数回の利上げを実施してきました。一方、その間に日銀は利上げを実施していません。米国と日本の金利差はどんどん広がっていったことになります。「預金をするなら金利の低い円より米ドルの方が魅力的」という状況が進んだということです。この点も米ドル円の為替レートに影響した可能性は否定できません。
外貨を買う際には、為替レートを動かす最新情報をチェックすることが大切です。
最新の為替レートはこちらから
金融資産状況、投資目的・目標額
個々の金融資産状況と投資目標も、外貨預金を開始するタイミングを決定する上で重要な要素となります。近々、日本円で使う予定のあるお金を外貨預金にすることは避けるべきです。ある程度の資金を手元に残しておかないと、為替差損が発生したときや引き出す時の手数料が思いのほか負担になることがあります。外貨預金のリスクを理解し、かつ余裕資金がある状況が始めるタイミングだといえます。
このように、外貨預金を始めるかどうか、そしてそれをいつから始めるかは、個々の投資家のタイミングによります。各専門家の調査情報や経済ニュース等を通じて、自分自身のリスク許容度と投資目標に最適な投資タイミングを導き出すことが必要になります。
必要な場合は、外貨預金を取り扱っている銀行のアドバイザーに相談することも一案です。
参考)外貨預金かんたん損益シミュレーションを活用すると元本割れにならない為替レートの目安を計算することができます。
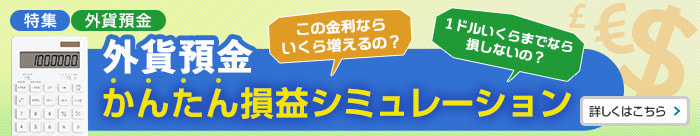
外貨預金を引き出すタイミング
外貨預金を引き出すタイミングは、預け入れ時に「ゴール(投資の出口)」を決めておくかどうかが重要になります。通貨の価値は常に変動するため、市場の動向を注意深く監視することも重要です。
預け入れ時より円安になった時
預金した外貨が日本円に対して高い価値を持っている時が最適な引き出しタイミングと言えます。預けた時点よりも円の価値が下がっている場合です。つまり、円安になっている状態であるので円に換金した時に受取額が増え、為替差益を得ることができます。ただし、ここで注意したいのが、為替手数料や引出手数料です。外貨を円にする際(引出時)には、手数料を含んだ為替相場であるTTB相場を適用するのが一般的です。為替手数料は、1米ドルあたり1円、50銭、25銭など銀行によって取引コストが異なります。
保有する外貨の政治経済状況に不安を感じた時
こちらは預け入れ時のタイミングと同じ話になりますが、現在の国際経済状況や政治情勢など、予測される将来の動向に不安を感じた場合、引き出しを検討するタイミングとなります。
実際に、事実情報が出ていないにも関わらず、観測情報だけで通貨が売られてしまうことがあります。為替相場は、投資家心理が影響する場合もあるからです。外貨を円に替えるタイミングの判断においては、自身がどのような不安を感じているのか、という観点も重要な材料になります。
投資目標のゴールを達成した時
外貨預金を引き出す適切なタイミングは、預け入れ当初に設定した具体的な目標金額に到達したかどうかが重要だといえます。「資産が思ったように増え、外貨ではなく円で保有することに切り替えたい」「老後生活に入り、安定資金が増えたので資産の評価額変動のリスクを取る必要が無くなった」などが外貨預金を終了する理由として挙げられます。
緊急のニーズが発生した時
他には緊急で資金が必要になった場合、外貨預金を引き出す決定を促すタイミングになる可能性があります。ただし、このようなケースでは、為替レートによっては計画していなかった損失が発生する可能性があることに留意する必要があります。
また、家計の財政状況やリスク許容度が変わった場合も外貨預金を見直す良い機会かもしれません。例えば、収入の状況が変化し、リスク許容度が下がった場合は、外貨預金を引き出し、より保守的な投資にシフトすることを考えても良い時期です。
以上のように外貨預金を始めるタイミング、引き出すタイミングは、様々な要因や状況によって異なります。したがって、外貨預金を始める前には、情報収集をすると共に、必要であれば銀行の相談員等のアドバイザーに相談し、投資計画をしっかり立てることを推奨します。
SBI新生銀行ではお客さまの運用プランに合わせた豊富な外貨商品をご用意しています。
この記事で紹介した預け入れや引き出しのタイミングを見極め、SBI新生銀行で外貨預金の運用をはじめてみてはいかがでしょうか?
SBI新生銀行の外貨預金はこちらから
外貨預金トップ\ ネットでカンタン口座開設 /
SBI新生銀行で今すぐ口座開設執筆者プロフィール


